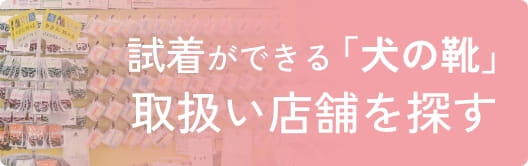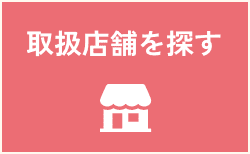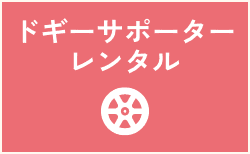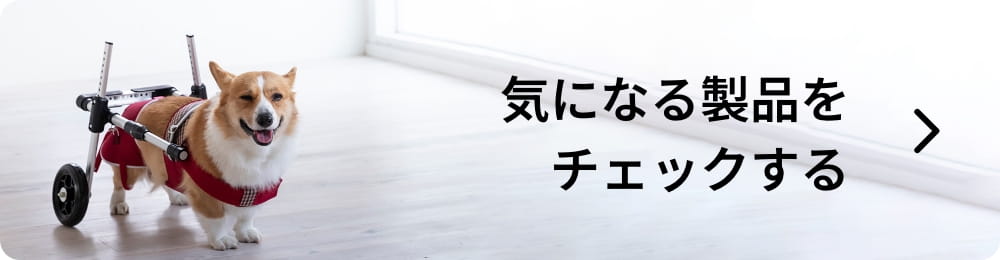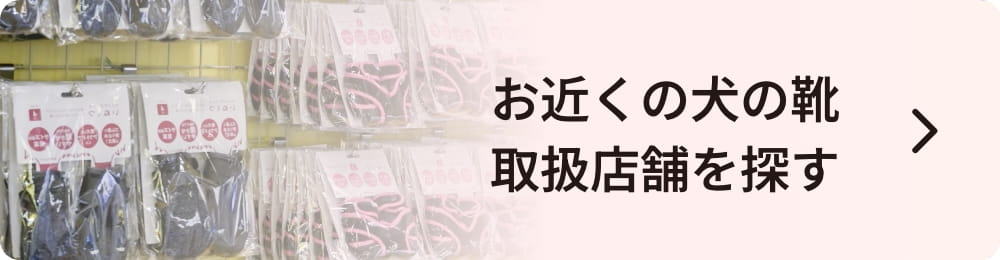犬の靴はオシャレだけじゃない:獣医師の視点でみる犬の靴の役割

もくじ
犬に靴は必要?その疑問に獣医師が答えます。

「犬に靴を履かせる必要なんて本当にあるの?」
そんなふうに感じたことがある飼い主さんも多いのではないでしょうか。確かに、犬の靴(ドッグシューズ)はまだ一般的とは言えず、オシャレやファッションの延長のように見られることもあります。
しかし実際には、犬の靴は肉球の保護や歩行の補助といった現実的なニーズから注目されてきた背景があります。
特に、アスファルトの高温や冬場の凍結など、犬の足元には私たちが想像する以上のリスクが潜んでいます。さらに、高齢犬や関節に不安のある犬にとっては、滑り防止や転倒予防といった実用的な目的で靴が活用されるケースも少なくありません。
都市部では、ガラス片や薬剤などへの接触リスクもあり、散歩中のダメージは決して無視できない問題です。
このコラムでは、こうした視点から「犬に靴を履かせることのメリット」や「適切な使用シーン」、「使用時の注意点」を、獣医師としての臨床経験をもとにわかりやすくご紹介します。犬に靴を履かせるという選択肢を、ぜひ一緒に考えてみませんか?
外を歩くとき、犬の足元には意外なリスクが潜む

お散歩は犬にとって欠かせない日課のひとつですが、私たちが思っている以上に犬の足元にはさまざまなリスクが潜んでいます。
まず夏場、アスファルトやコンクリートの路面温度は、想像以上に高温になり、肉球がやけどを起こすことがあります。実際、気温が30℃前後の日でも、路面の表面温度は60℃を超えることがあり、数分歩いただけで火傷のような損傷を受けることもあるのです。マンホールなどの金属部分は特に注意が必要です。
一方で、冬には逆のリスクも。気温の低下による“しもやけ”や、凍結した路面で滑って転倒する危険性があります。特にシニア犬や関節に不安を抱える犬にとっては、滑りによる転倒がケガや痛みの原因となることも珍しくありません。また、地域によっては道路にまかれた融雪剤(塩化カルシウムなど)が肉球に刺激を与えることもあるため注意が必要です。
加えて、都市部ではガラス片や鋭利な石、農薬や除草剤といった化学物質との接触リスクも無視できません。
散歩のコースや公園、駐車場など、日常的に歩く場所にも思わぬ危険が潜んでいます。
こうした足元のリスクから犬の肉球を守る手段のひとつが「犬用の靴」です。もちろんすべての犬に常に必要というわけではありませんが、特に夏・冬・舗装路の長距離散歩などの特定の条件下では、有効な選択肢となる場合があります。
高齢犬(シニア犬)にとっての靴のメリット
シニア犬にとっては、靴は生活の質(QOL)を支える補助具としての役割が期待できます。
年齢とともに後肢の筋力が低下したり、関節や神経の機能が衰えたりすることで、足元がふらつきやすくなる犬は少なくありません。
こうした犬にとって、靴は滑りやすい床での転倒を防ぎ、歩行を安定させるためのサポートツールになります。とくにフローリングなどの滑りやすい素材の床では、足元を踏ん張れずに転倒するケースも多く、靴のグリップ力が支えになる場面は多く見られます。
また、後肢の神経障害や関節の変形などで足を引きずるようになった犬では、足先の擦過傷や肉球の損傷が起こることがあります。靴を履くことでそうしたトラブルを未然に防ぐことができ、日常のケアもしやすくなります。
さらに、靴の着用により、屋外での歩行時の安定性を高めたり、寝たきりになりがちな犬の足先を保護したりするといった効果も期待できます。シニア犬にとって、靴は単なるアクセサリーではなく、身体的な負担を軽減する“実用的な道具”として機能するのです。
室内で靴を使うという選択肢

犬の靴というと、屋外での散歩や外出時に使うものというイメージが強いかもしれません。けれど実際には、室内環境においても犬用の靴が役立つ場面は少なくありません。
特にフローリングやタイルなどの滑りやすい床材の上では、犬が踏ん張れずに足を滑らせてしまうことがあり、これが関節や脊椎への負担につながることもあります。後肢の筋力が低下したシニア犬や、股関節・膝関節に不安を抱える犬にとっては、滑りによる転倒が再発性のケガや悪化を招くリスクになります。
実際の診療現場でも、「フローリングで滑って転んでから、破行(びっこ)を引くようになった」という相談をよく耳にします。私自身、出張手術で多くの犬の膝関節疾患に関わるなかで強く感じるのは、こうした日常のフローリングなどでの転倒が膝蓋骨脱臼や前十字靭帯断裂といった整形外科的疾患の一因になっているケースが少なくないということです。
完全な予防は難しいものの、滑りや踏ん張りにくさを軽減することは、関節への継続的な負担を和らげる一助となります。室内靴は、そうした日常的な関節保護の“習慣化できるケア”として、十分に効果が期待できます。
また、神経疾患や整形外科的な疾患によって足先を引きずる犬では、室内でも肉球の擦過傷や皮膚損傷を起こすことがあり、靴がその保護手段として有効に働くケースもあります。
さらに、飼い主が床を清潔に保ちたいというニーズや、他のペットや小さな子どもと暮らしている家庭での「衛生管理」の一環としても、室内靴が役立つことがあります。もちろん、装着時間や犬の反応には個体差があり、無理なく、犬が快適に過ごせる範囲での使用が前提です。
室内での靴の活用はまだ広く知られていない側面かもしれませんが、犬の関節や足元を守り、生活環境に適応させる手段のひとつとして、ぜひ選択肢に加えてみてください。
靴を使う際の注意点とアドバイス
犬に靴を履かせることは、状況によってさまざまなメリットがある一方で、使い方を誤ると皮膚トラブルやストレスの原因になる可能性もあります。
そのため、「適正なサイズ選び」「使用時間の管理」「慣らし方」といった基本的なポイントを押さえることが大切です。
まず最も重要なのがサイズとフィット感です。大きすぎる靴は脱げやすく、小さすぎると血行を妨げたり、摩擦による擦れや裂傷の原因になったりします。できれば足裏だけでなく、足首や甲までしっかり採寸した上で選ぶと安心です。
また、いきなり長時間履かせるのではなく、最初は数分から慣らしていくのが基本です。多くの犬は初めて靴を履くと違和感を覚え、ぎこちない歩き方をしたり、脱ごうとしたりするため、“慣れ”のステップを踏んであげることが大切です。
食事やおやつの時間に靴を履かせるなど、ポジティブな場面と組み合わせることで受け入れやすくなることもあります。
靴を履かせたまま長時間放置することは避けるべきです。通気性の低い素材の場合、蒸れや湿疹、かぶれのリスクが高まるため、特に暑い季節には注意が必要です。散歩後や使用後は靴の内側と犬の足を清潔に保ち、皮膚に異常がないかこまめに確認しましょう。
また、滑り止め付きの靴であっても、床材や犬の歩き方によっては逆に滑りやすくなるケースもあります。実際の使用感を慎重に観察し、合わないと感じた場合は無理に使い続けないことも大切です。
さらに、たまに見られるケースとして、脱いだ靴や靴下を犬が誤って飲み込んでしまうトラブルがあります。
特に好奇心旺盛な若齢犬や、ストレスのある状態の犬では、靴を「おもちゃや噛む対象」として扱ってしまうことがあるため、使用後は必ず犬の手の届かない場所に保管しましょう。万が一飲み込んでしまった場合には、速やかに動物病院を受診してください。
犬にとって靴は“当たり前のもの”ではありません。だからこそ、飼い主の配慮と工夫があってこそ、靴は有効な道具として機能します。愛犬が無理なく快適に過ごせることを第一に考え、靴という選択肢を上手に活用していきましょう。
まとめ ― 必要な犬に、適切な形で
犬に靴を履かせるということは、すべての犬に必要なわけではありません。
けれども、暑さや寒さ、滑りやすい床、関節や神経の疾患、高齢化による身体機能の低下など、日常生活の中で犬の足元に潜むリスクに対して、「靴」が果たせる役割は確実に存在しています。
私自身、獣医師として多くの症例と向き合う中で、靴によって肉球の損傷や転倒のリスクが軽減されたケース、靴を履くことで活き活きと楽しそうに歩けるようになった犬の姿を何度も見てきました。
そして同時に、「靴が合わなかった」「履かせ方に苦労した」というご相談もまた少なくありません。
大切なのは、「絶対に必要か」ではなく、「この子にとって役立つ可能性があるか」を考えること。
そして、もしその可能性があるならば、正しく選び、無理のない形で使うこと。それが、愛犬にとって快適で安全な毎日につながっていくと感じています。
犬の靴は、今や“特別なもの”ではなくなりつつあります。
飼い主の皆さんの判断と工夫次第で、愛犬の足元から生活の質(QOL)を支えるツールとして機能させることができる——そんな選択肢があることを、どこかで思い出していただけたら嬉しいです。
本記事の執筆者

Polaris Vet 代表 獣医師 渡邉 史恩
全国の動物病院やペット関連企業に向けて、獣医師による専門的なサポート事業を展開中。自身も出張外科診療を行い、全国各地の病院から依頼を受けて数多くの膝関節疾患をはじめとした手術に携わっている。現場に根ざした視点で、動物と飼い主に寄り添う医療とケアのあり方を日々追求している。
📰 関連コラム:
この記事をシェアする